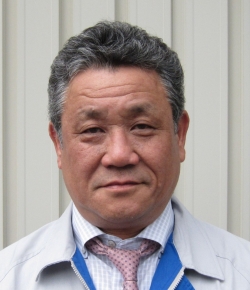気になるキーワードを入力してください
建産EYE
2014/10/03
建設物が完成したときの達成感は何事にも代えがたいもの
西高速金近トンネル補修作業所
淺沼組大阪本店 作業所長 藤原誠氏
高度経済成長時代に建設された多くの高速道路、トンネル、橋梁、堤防などの公共施設の老朽化が進み、メンテンス時代に突入したといっても過言ではありません。
中国自動車道の金近トンネルの補修工事を進めている淺沼組の作業所長の藤原誠氏に補修工事にまつわるお話や同社の経営理念、社会貢献事業などに加え、今後の建設業界のあり方などをお聞きしました。
――今回の金近トンネルでの工事は新設ではなく、補修工事ということでいろいろと戸惑いやご苦労が多いでしょうね。
確かに、これまでは新規に構造物をつくる工事がほとんどでした。今回の工事は、矢板工法によって施工されたトンネルについて、背面に空洞が確認された箇所に裏込注入を行うものです。中国道の下り線において5kmほどの区間を1車線通行にして12時間(7時~19時)規制を行い工事を進めています。高速道路の場合、土・日・祝日は交通規制が行えませんので、休工としています。
 ――供用中のトンネル内での工事、危険との隣り合わせでもあり、非常に神経を使うでしょうね。
――供用中のトンネル内での工事、危険との隣り合わせでもあり、非常に神経を使うでしょうね。
供用中の高速道路での作業ですから、車は高速で走っており、もし物を落としたりしたら、運転手さんが急ブレーキをかけ、大事故につながりかねません。それだけにミスが絶対にないよう安全第1をモットーに細心の注意を払って作業を進めています。事故を起こせば、企業にとって致命傷になりかねません。しかも昨今は工事量が減ってきていますので、次の受注につなげるためにも、事故は避けなければなりません。安全に加え、良いものをつくって提供することが強く要求されます。また作業側にとっても危険を伴う仕事だけに、労働災害防止にも注力しています。
――協力会社や職人のモチベーションを高めるため、いろいろとご努力されていると思いますが。
この現場で働く職人さんは20人位ですが、大きな現場のときは、安全週間にはみんなから標語を募集したり、現場で優秀な職人を表彰したりして現場での意識の高揚を図っていました。また打ち合わせを十分に行い、効率よく仕事を進め、仕上げを促進して利益をあげることです。それによって当社も儲かるし、協力業者さんにも利益を配分できます。いろいろな工夫をこらし、モチベーションが高められるよう力を注いでおり、関係者全員がこぞっていい関係を築けるよう日々の努力が欠かせません。
――職人不足に短期的、長期的にどのように対応していかれますか。
短期的には、少ない人数でどうすれば効率的に仕事が進められるかをできるだけ早い段階から考えて、工程的にいろんな業者さんと折衝して、来てもらえそうな時期に人を集めてやっていく。新設の現場でしたら、工場でつくったものを現場に持ってきて据え付けるとかしていけば作業量も減らせ、効率化が推進できます。つまり早い目に考えて打ち合わせをしながらやっていくことが大切だと思います。長期的には、魅力ある建設産業に育て上げることでしょうね。そのためには、技能労働者を育成し、どうすればもっと誇りを持てるかとか、労働に対する対価額に問題はないかなど、常に適正を意識すると同時に、業界全体が迅速に対応していかないと、人数を増やすどころか、減少に歯止めがかからなくなります。また機械化の推進もこれからの課題で、関係企業や研究機関とのタイアップなどで、やれる分野から早急に取り組むべきだと思います。
――業務上の施工ミスや労働災害防止のポイントは何でしょうか。
施工ミスについては、次の段階に進むまでのチェックを確実にすべきです。人間のうっかりミスは避けて通れず、それを防止するため、一人だけに任せるのではなく、何人かの目で見てチェックしていくことが施工ミスを減らすのに最も有力な方法だと思います。やはり2重3重のチェック体制をとること、これがミスを防ぐ最も適切な方法といえるでしょうね。
労働災害の防止に関しては、基本的には声掛け運動や見える化をやっています。社員を含めて協力業者など多くの目で見て、危険なことをしている人を見たら注意をして事故を防いでいくことが大切だと思います。見える化でいえば例えば高速道路のトンネル内には通信線等がありますが、作業時に高所作業車が接触しないように、移動のたびに操作者が認識できるようカラーコーン(上部確認と書いてある)を設置するよう義務付けています。
――淺沼組は随分、伝統のある会社と伺っていますが。
創業122年、創立77年ですが、スタートは江戸時代の柳澤藩に仕えた淺沼家に由来します。祖先は柳澤藩が長野県の甲斐から大和国郡山、現在の奈良県大和郡山市へ国替えになったのに伴い移転、普請方として仕えました。明治に入り、創業者である淺沼幸吉は普請方から棟梁に転身し、明治25年に淺沼組として建築請負業の看板を掲げ、昭和12年に株式会社淺沼組を設立しました。
――経営理念についてはいかがですか。
創業者、淺沼幸吉が「仕事が仕事を生む」という言葉を残しています。立派な仕事をすることで組の信用が生まれ、その信用こそが次の仕事をいただける最大の資本になるという考えです。
創業理念と致しましては、「和の精神」と、「誠意・熱意・創意」との2つを掲げています。
「和の精神」は、和して同せずで、人と調和しても、人の意見に同調したり、妥協したりせず、主体性を以って事にあたるということです。
「誠意、熱意、創意」は正直に熱心に(誠意)、意気込み思い入れ(熱意)、新しい思いつきや独創的な考え(創意)を以って事にあたるということです。
またコーポレートスローガンとして掲げているのは「人・都市(まち)・自然のシンフォニー」です。創業理念のもと、人と環境を大切にする〝創環境企業〟として、事業活動を通じ社会の安全と幸福の増進に貢献できるよう心がけています。
――会社として誇れることは。
創業以来、幾多の苦難がありましたが、建設業一筋でやってきた点でしょうか。それは創業者の理念である「仕事が仕事を生む」を脈々と受け継いできたからです。
初代淺沼猪之吉もこういっています。
「建築という仕事はその場限りのものでなく、まして私一代のものではない。将来、末永く世間に残るものだ。いい加減な仕事をしては、お施主様に申し訳ないばかりでなく、孫子の代まで世間の笑いものになる」
全社でこの言葉を肝に命じて、日々努力しています。
――御社の社会貢献への意識は高いですね。
災害に強い街づくり、さらなる高品位環境の創造など、社会からの要請に応えるために、絶えず技術開発や技術力の向上に取り組んでいます。ひとたび災害が発生すると、これまで蓄積してきた技術と経験・ノウハウを生かし、被災地復興の一助となるよう迅速に行動するよう心がけています。またよりよい環境の創造と保全のために、CO2排出量の削減や再生資材の有効利用等に取り組むとともに、昨年度からは、エネルギー事業として太陽光発電事業に参画し、再生可能エネルギーの導入にも力を注いでいます。
一方、日常業務や交流の場を通じた対話をはじめ、市民・親子や海外留学生対象の現場見学会・インターンシップの受け入れ・地域清掃活動への参加等さまざまな形のコミュニケーションを通じ、社会との調和を促進するとともに、社会の声を事業活動に反映したいと考えています。
――所長に共通した誇りについて。
作業所で働く当社職員はもとより、協力会社も含め、すべて大切なパートナー(家族)です。その責任を背負い、お客様や地域社会と向き合う。そのときに自己のみの利益を考えるのではなく、お客様やその建築物を実際に使う人々にとってよりよい判断をしなければならない。大変つらく厳しい立場ではあるものの、それを乗り越えて、建設物が完成したときの達成感は何事にも代え難いものです。その責任と権限を会社から託されたことが誇りだと思います。
――ご自身の誇りは何でしょうか。
社員や業者さんなど関係者が一致団結して、できるだけいいものをつくろうと知恵を出し合って土木の構造物をつくっていくわけですが、完成したときにお施主さんや地域の方からいいものをつくっていただいたと喜んでもらえ、それが30年、40年とずっと残っていく。そういう構造物をつくっていっていることに誇りを感じています。
――今日までの実績について。
若い頃は下水道が普及しつつある時代でしたので、下水道の仕事が多かったですね。最近では京都縦貫自動車道京都第二外環状線長岡京工区、阪神高速淀川左岸線大開出入路下部工事など、西日本高速道路や阪神高速道路の工事などを4つぐらい続けてやらせていただいています。
――専門工事業者や職人に対するご要望があればお聞かせいただけますか。
当社でも協力業者に対しては現場で評価をして、基本的には評価点の高い業者から発注していくようにしています。公共工事の一日当たりの労務単価は決まっていますので、皆さんにスキルアップしていただいて、当社の職員も減ってきているなかで、ある程度任せられる専門業者や職人さんがもっと増えてくれれば効率化もより進み、いいものができるのではないかと思います。
――どうもありがとうございました。
【プロフィール】
藤原誠(ふじはら・まこと)=1957年生まれ。大阪府出身。立命館大学理工学部土木学科卒。1981年淺沼組入社。