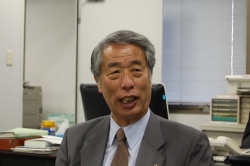気になるキーワードを入力してください
建産EYE
2014/12/10
一般社団法人大阪府警備業協会若林清会長 公共工事の増加。今こそ、警備員の待遇改善を。
工事現場において、建設作業員とともに重要な役割を果たすのが警備員。警備業法により2号業務と呼ばれ、工事車両の誘導などをはじめ、現場の安全を確保する役割を果たす「縁の下の力持ち」だ。
しかし、公共工事の増加に伴い、作業員ととともに警備員においても人手不足が発生し、社会保険の未加入問題を受け、警備業全体で社会保険の加入促進に向けた動向があるものの、警備会社の経営状況が改善されない中で加入できないなど、警備員の現状は厳しさを増している。
公共工事が増加する中で、待遇や人手不足など、警備員の厳しい現状と、今後の展望について、一般社団法人大阪府警備業協会の若林清会長にお話を伺った。
――工事現場において、警備員が懸命に働く姿を見かけるが、現場で従事する警備員の現状について。
工事現場で従事する警備員は、主に交通誘導や工事車両の誘導などを行い、身の安全を守りながら、現場の安全をサポートしている。だが、夏の暑い日や雨の日でも従事する大変な仕事であり、公共や民間、あらゆる現場で労災事故が多いのが現状だ。
労災事故は、去年一年間で35名(対前年度比で29・6%増)の方が亡くなっている。安全対策を取っているにもかかわらず、いねむり運転の車にはねられるといったようなもらい事故が多くなっている。熱中症で亡くなった警備員もいる。
このように交通誘導業務は、施設や貴重品の運搬業務に比べて、警備の中で一番過酷な労働であるにもかかわらず、警備料金が安い。大震災が起こり、復興事業が進む東北では上昇しているが、大阪では10年前から比較しても上がっていない。横ばいどころか、むしろ下がっている状況にある。公共工事は増える傾向にあるのに、今の状態では極めて低い。
――なぜ、警備料金が上がらないのか。
積算の基本が間違っているからだ。公共工事における労務単価は、最低賃金を基に計算されているが、必要な管理費等がほとんど加味されていない。また、一年の中で、年度末の2~3月に入札が一番多く集中する。その時の安い入札で料金が設定されてしまう。工事が増える中で、秋頃に上げなければならないが、なかなか上げてくれない。
2号業務に区分される交通誘導を主とする警備会社は、中小零細企業が多く、経営が悪くなっている。ましてや、過酷な労働である故、人手も集まらない。そこを何とか変えていかないといけない。
――社会保険の加入について、国交省や建設業界から促進が要請されているが、警備業界としての対応は。
交通誘導を主とする警備会社の経営状況が悪化している今の状態では、社会保険に加入できないのが現状である。中小零細企業が多く経営が苦しい。加入するなら、賃金を15%アップしないといけない。しかし、現状は5%のアップがいいところで、これはかなり大きい。
警備料金の8割は労務費で、その中で雇用や教育を行っていかないといけない。社会保険に加入させたら赤字になる。どうしても賃金のアップが難しい。
公共工事の現場では、国交省からの未加入排除の方針により、社会保険加入の証明書を持っていないと、仕事につけない。社会保険の加入を促進させるためには、警備料金を上げてもらうことが必要だ。
――警備員の実情を改善させるには、どうすればよいか。
公共工事において、現場の安全対策として警備員が必要であることは、国も認めている。だが、他の施設や貴重品の運搬業務に比べ、交通誘導業務は大変な仕事であるにもかかわらず、料金が安い。
平和な日本では、安全という部分は削りやすい。どの現場でも、安全に対してコストをかけてくれないから、どうしても料金が安くなる。改善のためには、警備業務に対する付加価値を認めてもらうことが必要だ。
警備業は、工事現場をはじめ、花火大会等のイベントや、警察がやっていた駐車違反の取り締まり、刑務所の管理まで、日本社会及び警察の下支えをものすごくしていると感じている。電車に例えると、レールが警察なら、枕木や砂利が警備業だ。どちらかがおかしくなると、社会全体がおかしくなる。
日本社会全体で安全に対する見方が低いように思われる。何かがあった時は危機管理が叫ばれる。常に安全意識を持ってほしい。公共工事が増加する一方で、交通誘導業務は劣悪な環境で働き、料金が安い。適正な積算による料金設定、待遇改善のために国や自治体、建設業界はもっと考えてもらいたい。
――警備員の人材確保について、若い人に来てもらうには。
生命と身体、財産を預かり、誇りを感じてもらう仕事として、若年層に仕事の魅力をどうPRしていくかだ。若年層へのPRは、同じ人材不足に悩む建設業と一緒である。
交通誘導業務は体力、集中力が必要であるが、3Kどころか5K、10Kの仕事。お年寄りなど年齢層が高くなっているのが現状である。中には笛を吹いて女性やこどもを安全に誘導することに誇りを感じてくれる人もいるが、日当で7~8千円がいいところ。それを考えると若い人はなかなか来てくれない。単価アップなどの待遇改善を訴えていくことが重要だ。
また、人手不足の中、今後は女性の活用を見直さないといけないと考えている。
――警備業法制度の問題点とそれに向けた対策の検討について。
警備業法により、人手が足りないからといって、人の貸し借りはできない。しかし、交通誘導業務の待遇の悪さや人材不足が深刻であり、規制の緩和が求められているところだ。
警備業法改正に向け、現在、全警協で配置基準と検定、共同実施における法制度、規制から育成、教育制度の4つの分科会にて、検討を進めており、来春までにまとめて警察庁へ要望することをめざしている。また、国会でも、「警備業の更なる発展を応援する議員連盟」ができ、ワーキンググループを立ち上げ、法制度改正に向けた議論を行っている。
――協会として、どのように取り組んでいくか。
大阪建設業協会やゼネコン各社に、今の警備員の窮状を理解していただき、適正な警備料金のお願いにまわることにしている。業界に対する申し入れは初めての取組みで、そこまでやらないといけないほど深刻な状況だ。せめて、社会保険加入の必要経費分は上げてもらわないと困る。
労災事故を防ぐために、会員会社に対し、事故が起きれば、速やかに報告を出し、会員会社で共有する。また、声かけ運動を展開していく。現場では、毎日朝礼を行い、様々な指示をしている。これはとても大事なことで、現場で従事する警備員にひと声かけることで、安全対策の徹底を図っていただくようお願いにまわっていく。
――今後の警備員及び警備会社の展望について。
建設業界は、この5~6年厳しく、公共工事が激減し、業者も減少してきた。しかし、安倍政権のアベノミクス効果や、相次いだ大震災の発生、台風や集中豪雨など自然災害の多発などから、公共事業の需要が高まり、国も強靱な国土の建設と国民生活の安全を構築するため、建設業者や土木業者に対する重要性を再認識し、国交省も技術者と後継者の育成に本腰を入れてきた。
協会としても、このような建設業界の変化に対応し、警備員の待遇改善に向け、建設業者にお願いにまわっていくつもりだ。
また、最も重要なのは、個々の警備員の能力を高めて、ユーザーへの期待に応えていくことである。そのためにも、警備員の教育を徹底し、資格を取らせ、警備業全体の質の向上を図っていきたい。
そして、若い人たちが警備業に来ていただき、希望を持てる業界にしていきたい。